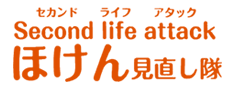介護資金
こんにちは、セカンドライフアタックほけん見直し隊です。
もしあなたが介護状態になったらどうしますか?
在宅介護で月平均 48,000円
施設で月平均 122,000円
介護期間平均61.1か月
合計 平均約580万円となります。
介護資金の準備はどのようにお考えでしょうか?
アンケートによると
1位 預貯金
2位 保険
預貯金は、90歳以上の方は、77.6%
保険は、60~64歳の方は58.7%
5位 不動産の売却
(公益財団法人生命保険文化センター2023年)
と、介護資金についての意識が高くなってきているようです。
健康寿命を延ばす努力はもちろんですが、資金の準備も
計画的にしておきたいですね。
1人暮らし
こんにちは、セカンドライフアタックほけん見直し隊です。
警察庁の集計で、「2024年1月から6月の
自宅で死亡した1人暮らしの人数」が、出ていました。
計3万7227人
うち15~64歳が23.7%
65~69歳が10%
70~74歳 15.1%
75~79歳 15.9%
80~84歳 14.9%
85歳以上 20.1%
不詳 0.2%
です。
発見まで日数は平均18日、
孤独死した方の家族を含めた社会とのつながりの希薄さ
が感じられます。
ご遺族の方の負担も大きくなります。
できるだけ日ごろから、親族の方と連絡を取ったり
地域での交流に参加したり 訪問サービスや老人ホームの利用
あとはお金の準備をしておきたいですね。
個人年金保険受取り一括?年金受取?
こんにちは、セカンドライフアタックほけん見直し隊です。
老後資金の積立として個人年金保険があります。
昔契約されたものは、お宝個人年金であり
積立利率が高く思った以上に増えています。
保険料払込終了後の受取方法を、一括受取と年金受取
どちらが得なのでしょうか?
まず一括受取りのメリットは一度にまとまったお金を受取れる
事でありリスク性商品で運用や、リフォーム等に使うことができます。
税金は、一時所得となり確定申告は1回で済みます。
年金受取は、受取金額が一括受取りより多くなり
確定申告は毎年必要ですが、雑所得となります。
運用はしたくない、使う予定もないという事であれば
年金受取がお得ですね。
健康寿命
こんにちは、セカンドライフアタックほけん見直し隊です。
厚生労働省が3年ごとに実施される調査で2024年12月に
2022年の健康寿命を公表しました。
全国平均で男性は72.57歳 女性は75.45歳
前回の19年と比較して男性は0.11年短く
女性は0.07年延びているそうです。
都道府県別では、男女の平均は1位が静岡県
残念ながら大阪は44位です。
それぞれ自治体が、住民の健康寿命を
伸ばそうといろいろ取り組みをしているようです。
楽しみながら続けられる方法で、健康寿命を延ばしたいですね。
成年後見人
こんにちは、セカンドライフアタックほけん見直し隊です。
先日新聞で、「成年後見人の選任を裁判所に求める首長申し立ての
件数が増えている」との記事がでていました。
成年後見制度は、判断能力が十分ではない高齢者を法的に支援する仕組みであり
家裁が選任した後見人らが本人に代わって財産管理や福祉サービスの
契約などを担います。
本来は家族等が申し立てをするのですが身寄りがない場合や頼れる家族
親族がいない場合は市町村長が申し立てすることができます。
申し立て総件数約4万件のうち首長によるものは23.6%で、子供による申し立て
の20%を超えています。
少子高齢化で首長による申し立てが必要な場合が増えているようです。
又、都道府県により大きな開きがあることも問題です。
戸別訪問や協議にかけたりという体制つくりの差が、あるようです。
孤独死や詐欺被害がどんどん増えないよう国でも何か対策が必要ですが、
自分でも、認知症や介護状態になってしまった時の事や、死後の事は
対策、準備はしておきたいですね。
高額療養費制度引き上げ
こんにちは、セカンドライフアタックほけん見直し隊です。
今年も多々改正があります。
8月から段階的に引き上げがあるのが、高額療養費制度です。
負担上限額が引き上げとなるのですが、具体的には
年収370万円~770万円の場合は約80100円が約88,200円
となり、年収1160万円以上の場合は約252,600円が約290,400円と
大きく上昇します。
26年8月からは年収の区分を細かくし2段階にさらに上限額を引き上げ
ていきます。
仕事をしながらぎりぎりの範囲で治療を受けている方にとっても
心配な改正です。
イデコ 続き
こんにちは、セカンドライフアタックほけん見直し隊です。
先日は、「退職所得控除の二重取り」で退職金より先にイデコを
一時金で受け取った場合の改正についての内容でしたが
今回は、退職金を先に受け取った場合の退職所得控除についてです。
既に22年4月に改正となっている内容です。
22年3月までは、退職金受給年を含めて15年以内にイデコの受給なら
退職所得控除の二重取りは不可でしたが、4月からは20年以内は不可
となっています。
イデコの受給開始が75歳まで伸ばせるようになっていますがどちらにしても
二重取りは難しくなっています。
この場合も金額、退職控除利用期間を確認する必要がありますね。
イデコ
こんにちは、セカンドライフアタックほけん見直し隊です。
2024年12月制度改正により、イデコ掛金の拠出限度額が
引き上げされました。
第2号被保険者の方は、月額12,000円から20,000円になります。
急いで、増額された方もいらっしゃると思いますが、
控除縮小期間が延びることはご存じでしょうか?
一時金を受け取る際の課税が強化されます。
退職金よりも先に受け取る場合に控除を縮小する期間を
現在の5年未満から10年未満に延ばされたのです。
手取り額が大きく変わる可能性があります。
退職金の受取時期、退職金控除の金額等よく確認して
思いがけず税金がかかってしまうことのないように
気を付けてくださいね。
2024年 為替
こんにちは、セカンドライフアタックほけん見直し隊です。
今年は なんといっても「円の独歩安」でした。
ドル円が今年7月に161.95円と37年ぶりの円安となり
プラザ合意を経た1986年12月以来の円安水準となりました。
1月1日は140.83円で始まりましたが結果的には
最高値、12月27日は157.89円です。
円安の要因はやはり日本の低金利だと思いますが
2025年はどうなるでしょう?
アメリカは今年利下げを開始、日本は利上げを開始
この流れが続くようなら多少は円高に向かいそうですね。
持ち主不明年金
こんにちは、セカンドライフアタックほけん見直し隊です。
2007年に社会問題となった持ち主不明の年金5095万件が
17年たった今も1713万件もあるそうです。
転職が多い 姓が変わった いろいろな名前の読み方がある
の3パターンは未統合の記録が多いようです。
厚生年金基金も未支給年金が多く本人から請求のない
分が今年3月時点で113万人に上るそうです。。
訓読みの名前が音読みで手続きされていた記録が死亡後に
判明し遺族が未支給の老齢年金を受け取った例があります。
「ねんきん定期便」で必ず確認しましょう。