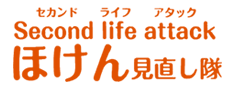セパレート帰省
こんにちは、セカンドライフアタックほけん見直し隊です。
年末の日経読者調査記事で「セパレート帰省経験」という
言葉がでていました。
夫婦が一緒に帰省せずそれぞれの実家ににだけ帰るという
もので6割の人が経験したことがあるそうです。
満足度は、想像通り女性の方が圧倒的に高く9割以上の方が
満足とのことです。
「義理の親子は他人」との考えも広がっているようです。
「寂しさもあるがお互いに気を使わず過ごしたい」
セパレート帰省をしたことも検討したこともないという
方は28.7%でした。
できれば誰かが一方的に我慢することなく
納得できるようその都度、気軽に帰省について話し合いができれば
いいですね。
高額療養費制度見直し
こんにちは、セカンドライフアタックほけん見直し隊です。
2026年夏以降、高額療養費制度の改正があります。
がんや難病など長期療養者や低所得者に配慮した内容とはいえ、
2027年夏以降は、上限額を決める所得区分を細かくし所得が
より多い人の上限額が上がり、所得区分ごとに
2.7~15%増額となります。
急激な負担増を抑えるために、あらたに「年間上限」を
導入しますが、治療費の負担が増える方がかなり増えそうです。
これからの老後は、治療費に介護費とダブルで負担増です。
3人に1人が貧困層になるといわれています。
準備をして安心な老後を迎えましょう。
障害年金
こんにちは、セカンドライフアタックほけん見直し隊です。
日本では障害をもつ可能性のある方は人口の
9.2%に相当するといわれていますが、実際に
障害年金を受給している方は障害者全体の約2%
程度という推計があるそうです。
対象外だと思っている、
手続きがややこしい等の理由で障害年金を
もらい忘れていませんか?
20歳から64歳の方で病気やけが、障害でお仕事や
日常生活に影響が出ている方で、障害年金1級2級に
該当しなくてもより軽度の3級や障害手当金を受給できる
事もあるようです。
年金事務所や相談センターで相談できます。
、ねんきんダイヤルでも
一般的な相談は受け付けているようです。
心不全パンデミック
こんにちは、セカンドライフアタックほけん見直し隊です。
「心不全パンデミック」とは、超高齢化社会の進展により心不全患者が
世界的に急増し医療システムに大きな負担を与える状態
を指します。厚生労働省もその対策を進めています。
心臓病でよく起こる病気で狭心症、不整脈、心不全、合わせて約8割。
多くの国で心不全が増えており
40歳以上の5人に1人が心不全になる、
65歳以上の入院理由の第一位、
30日以内の再入院が24%
1年以内の再入院は60%
という統計がでているそうです。
治療も進化しているとはいえ、ずっとつきあっていかないと
いけない病気であり、高い薬を飲み続ける必要が有る場合も多いようです。
できる限りの予防と、ちょっとおかしいなと思ったら
早めの受診ですね。
相続税
こんにちは、セカンドライフアタックほけん見直し隊です。
この10年で相続税対象者が3倍弱まで増えているそうです。
地価の高騰で持ち家や土地の資産価値が上昇したことが
大きく影響しています。
相続税は相続人の人数によって異なる「基礎控除額
(3000万円+600万円×法定相続人の数)」を引いた
課税遺産総額にもとづいて計算されるため二次相続時子供一人なら
基礎控除額は3600万円となり、より相続税がかかりやすくなります。
亡くなる人も増え相続問題の相談件数も
増えているようです。
親は遺言書作成などで相続問題を防ぎ、子供とよく
相談し相続税負担にも対策しておく必要が有りますね。
がん治療
こんにちは、セカンドライフアタックほけん見直し隊です。
がんの3大治療とは、手術 放射線治療 抗がん剤治療ですよね。
これに1つ加わり現在では4大治療ともいわれるようになりました。
近年、「免疫チェックポイント阻害薬」が登場し保険承認
されたためこれに「免疫療法」が加わったのです。
免疫療法うち保険診療になるのは1部ですが、、。
免疫チェックポイント阻害薬とは、がん患者さんの体の中では
がんやウィルスから守ってくれるT細胞が
働いていない状態なのですが、免疫チェックポイントを阻害することで
T細胞のブレーキを外して元気にするというものです。
医療は日進月歩。
今は効果的な治療がない方も希望をもって待ち続けようと
思える時代です。
まずはどんな治療になっても保険が受け取れるがん一時金の準備は
重要です。
今の保険で準備できていますか?
高齢者の死因
こんにちは、セカンドライフアタックほけん見直し隊です。
高齢者の死因は、
1位はがん、2位は心疾患
3位は老衰、4位は脳血管疾患
5位は肺炎、6位は誤嚥性肺炎
です。(R3年 厚生労働省)
4位まではご存じの方は多いと思います。
4位の 肺炎は病気などで免疫力が低下すると感染しやすい病気
ですが、5位の誤嚥性肺炎は聞きなれない方も
いらっしゃるのではないでしょうか?
細菌が唾液や飲食物と一緒に肺に流れて起こる肺炎のことです。
これは飲み込む機能の衰えから生じます。
誤嚥性肺炎がきっかけで体力が低下し介護が必要になることも
あるようです。
喉や口の筋トレや唾液腺マッサージ、歯科検診など
自分でできる予防を是非始めましょう。
イデコ 改正
こんにちは、セカンドライフアタックほけん見直し隊です。
今年6月に年金制度改正法が成立しました。
公布から3年以内の政令で定める日施行と
なっており未定ですが、2027年~スタート予定のようです。
変更点は
①加入年齢が65歳未満から70歳未満へ変更
②掛金の引き上げで、第一号被保険者は68,000円から75,000円へ
第2号被保険者は会社に企業年金がない場合は23,000円から62,000円
あと退職金税制は2026年から改正です。
退職所得控除の5年ルールが10年へと変更となります。
今までは4年あけて退職金等を受けとれば退職所得控除を重複
して計算できていたのですが、9年あけないと重複できなくなります。
老後資金の準備をするにあたっては、それぞれメリットデメリットを理解して
おきましょう。
保険の特約
こんにちは、セカンドライフアタックほけん見直し隊です。
保険には、メインの保障内容である「主契約」と、オプション契約の
「特約」で構成されています。
特約は大半は有料ですが、無料で利用価値の高いものがあります。
まずは、「リビングニーズ特約」です。
余命6か月と診断されたら、死亡保険金の1部あるいは全部を
生前に受け取れます。
次に、「指定代理請求特約」です。
被保険者がケガや病気などで、手続きができない場合
代理人が請求できます。
指定代理請求特約は、少数ですが付加されていない方が
おられます。
是非1度、契約中の保険を確認してみてください。
日米政策金利
こんにちは、セカンドライフアタックほけん見直し隊です。
アメリカは17日のFOMC(米連邦公開市場委員会)で
6会合ぶりに0.25%の利下げで4.00%~4.25%に決定、
日本は19日金融政策決定会合で予想通りの
0.5%の維持が決定しました。
まだまだ金利差は大きく外貨建て商品の魅力は引き続き
ありますし、円建ての一時払い保険の魅力も出てきました。
為替のリスクが取れる人も取れない人も選択肢が
広がってきました。
どちらもリスクをよく理解して検討してください。